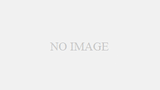3Dプリンターの造形物に出るレコードのような規則正しい横線、その原因はZ軸のズレです。この現象は「Zバンディング」と呼ばれています。
リードスクリューの曲がりや芯ズレなど、Z軸の機械的な問題で発生するんです。
Zバンディング以外に、Z-wobble(Z・ウォブル)やウォバリング(Wobbling)という名前で呼ばれています。
光の角度によって目立ったり目立たなかったりするので厄介ですが、原因さえ特定できれば解決は意外と簡単です。
この記事では、Z軸のズレで横線が出るメカニズムから、具体的な診断方法、そして解決法まで、すべて解説していきます!
Z-Banding(Z-wobble)とは?
まずは、この現象がなぜ、どのようにして発生するのか、理解しましょう。
Z軸の周期的なズレが引き起こす現象
Z-Bandingは、「Z軸方向」の移動が周期的に不安定になることで発生します。
FDM方式の3Dプリンターでは、Z軸はステッピングモーターが回転させる「リードスクリュー(ネジ棒)」で制御されています。このリードスクリューに何らかの異常があると、造形ヘッドやベッドが設定された高さからわずかにズレてしまうんです。
このズレは、リードスクリューの回転サイクルに合わせて発生するため、造形物の側面に一定間隔の「縞」として現れます。この周期的な縞模様こそが、Zバンディングの最大の識別点です!
発生箇所はZ軸のリードスクリューまわり
Zバンディングの原因は、ほぼ間違いなくZ軸の駆動システムにあります。リードスクリューの曲がりや、周辺部品の取り付け精度が不完全だと、Z軸の動きが乱れてしまうんです。
具体的には、以下のような部品が関係しています。
- カプラー(モーターとスクリューを繋ぐジョイント)
- モーター本体とその取り付け台座
- ガイドレールやリニアレール
- リードスクリューを支えるベアリング
これらのどれか一つでも精度が狂っていると、美しい造形は難しくなってしまいます。
Z-Bandingと似た症状の見分け方
Zバンディングと間違えやすい症状は、その周期性と発生箇所で区別できます。
リングイング(ゴースティング)との違い
造形ヘッドやベッドが急加速・急減速する際の振動が原因で起こる現象です。鋭い角を曲がった後や文字の周囲などXY軸の動作が急変した部分に不規則な波紋のような影として現れます。
見分けるポイントを押さえておきましょう。
- 縞の間隔が一定ではない
- Z軸の高さ方向とは直接関係がない
- 角や文字の周辺など、特定の場所だけに出る
押出ムラとの違い
フィラメントの吐出量が不安定になることが原因で、層の厚みが不規則に変化します。横線や段差の間隔が不規則で周期性がないのが特徴です。
こんな原因で発生します。
- ノズルの詰まり
- ホットエンドの温度変動
- フィラメント径のばらつき
エクストルーダー系の問題が多いですね。
目視チェックポイントと簡易テスト
実際に問題がZバンディングかどうかを判断するための、簡単なチェックをしてみましょう!
周期性の確認
最も重要なのは、横線が規則的な間隔で現れているか確認することです。定規を当てて、縞模様の間隔が常に一定であれば、リードスクリューの回転周期に由来するZバンディングの可能性が極めて高いです。
自分でできる切り分け診断
Z軸の手動確認から始めてみましょう。プリンターの電源を切り、手でZ軸をゆっくり上下させます。スムーズに動けばOKですが、途中で引っかかる感じがあれば要注意です!
- スクリューの転がし確認:リードスクリューを外し、平らな机の上で転がします。波打つように転がるなら、スクリュー自体の曲がりが原因です。
- カプラー・芯ズレの確認:モーターとスクリューを繋ぐカプラーを緩め、軸がまっすぐ一直線上に接続されているかを目視で確認します。わずかでもズレていたらアウトです!
- ノズル温度変更テスト:印刷温度を5℃変更してテストプリントを行います。縞模様の出方が変わるようであれば、押出ムラや温度変動が原因の可能性が高いです。
この診断テストによって、Zバンディングであると確定したら、次は原因を特定するステップに移ります。次章では、Zバンディングを引き起こす3つの主な要因を、「機械」「押出」「設定」の視点から詳しく解説していきます。
Z-Bandingの3つの主な原因
Zバンディングの最大の特徴は、造形物の側面に周期的な横縞が現れることです。この縞模様の間隔は、Z軸のリードスクリューのピッチ(ネジ山の間隔)によって決まります。
機械的要因(最優先でチェック)
Zバンディングの発生源として、最も高い確率で関係しているのがZ軸を構成する物理的な部品の不具合です。私の経験上、8割以上はここに原因があります!
- Zリードスクリューが曲がっている/傾いている
- モータ軸とスクリュー軸の心が合っていない(芯ズレ)
- カップラーが偏心している/押し込み過ぎている
- Z軸ガイドの固定が歪んでいる
- Z軸が片持ち構造でたわんでいる(例: Ender3など)
特に最初の2つ(スクリューの曲がりと芯ズレ)は、Zバンディングの大半の原因です。スクリュー自体が少しでも曲がっていると、回転するたびに遠心力が働き、Z軸全体を一定周期で前後左右に押し引きしてしまいます。
また、ステッピングモーターの軸とリードスクリューの軸が一直線上にないと、スクリューが大きく「暴れる」ことになります。組み立て時にここをテキトーにやってしまうと、後で泣きを見ることに…。
カプラーの締め付けが不均一だったり、軸を深く押し込みすぎて歪みを生じさせていることもあります。特に安価なフレキシブルカプラーは、芯ズレを吸収しきれずに問題を悪化させる場合があります。
押出・エクストルーダー要因
押出が不安定になると、ウォバリングと似た段差や縞模様が出ることがあります。これはZ軸のズレではなく、「吐出量が層ごとに違う」ために生じる現象です。
- ノズルの詰まり・摩耗・汚れによる押出量ムラ
- フィラメント径のばらつき(安価フィラメントに多い)
- ホットエンド温度の変動
ノズル内部にコゲカスなどが溜まると、安定した量の樹脂が吐出されません。フィラメントの太さが途中で変わると、同じ押出量でも実際にノズルから出る量が変わります。PIDチューニングが不十分な場合や、ファンからの風がノズルに干渉している場合、温度が安定せず樹脂の粘度が変わります。
スライス・設定要因
ソフトウェアの設定によって、ハードウェアのわずかなズレが増幅されている場合があります。意外と見落としがちなポイントなので要チェックです!
- レイヤー高さがリードスクリューのピッチと合わない
- ZリフトやZ-hopが頻繁すぎる
Z軸リードスクリューの1回転の移動量と、スライサーで設定したレイヤー高さの相性が悪いと、Z軸のモーターが毎回「同じ場所でわずかなズレ」を生じさせます。数学的に割り切れない設定をしていると、モーターが半端な位置で止まろうとして微妙にブレるんです。
また、ノズルが造形物を避けて上に持ち上がる「Z-hop」設定が頻繁すぎると、Z軸に繰り返し負荷がかかり、一時的なズレを引き起こします。便利な機能ですが、使いすぎは禁物ですね。
Z-Bandingの解決法
いよいよ解決策です!「最も効果的で確実な改善策」から順に実行していきましょう。
機械的対策
機械的な問題には、物理的なアプローチが一番効きます。ソフトウェアでいくら調整しても、ハードウェアが曲がっていたら意味がないですからね!
リードスクリューを真っ直ぐなものに交換(最優先)
曲がりが確認されたら、迷わず新しいものに交換しましょう。精度の高い「TR8×8」などの規格のスクリューを選ぶことで、精度が飛躍的に向上します。私もこれで一発で解決した経験があります!数千円の投資で劇的に改善するので、コスパ最強の対策です。
スクリュー上端を固定しない(フローティング構造)にする
これが多くのプリンターで効果的な秘策です!Z軸の上端にあるベアリングやブラケットの固定を外し、スクリューが自由に動ける状態にします。これにより、スクリューのわずかな曲がりから生じる揺れを吸収し、Z軸に伝わりにくくします。
具体的な手順はこちらです。
- Z軸上端のベアリングホルダーのネジを緩める
- スクリューが上下に数mm動ける遊びを作る
- 完全に外してしまうのではなく、軽く保持する程度に
最初は「固定を外して大丈夫?」と不安でしたが、実際にやってみると驚くほど効果があります!
Zモータブラケットの歪みを修正/金属製に交換
モーターの取り付け台座が樹脂製などで歪んでいる場合、それがZ軸の芯ズレの原因になります。金属製のものに交換したり、取り付けネジを均等に締め直したりすることで、軸の安定性が増します。特にEnder3系のプリンターでは、アルミ製のブラケットに交換するだけでかなり改善しますよ。
Z軸のグリスアップ・清掃
リードスクリューやナット部分に異物やホコリが溜まると、Z軸の動きを阻害します。定期的に掃除し、テフロン系の専用グリスやシリコングリスを薄く塗布しましょう。ただし、つけすぎるとホコリを吸着してしまうので、ティッシュで拭き取るくらいの薄さがベストです!
押出・ホットエンド対策
押出系の問題は、樹脂の流れを安定させることで解決します。
ホットエンドのPIDチューニングを実行
プリンターのファームウェア設定からPIDチューニングを実行し、ノズル温度の安定性を高めます。これにより、温度変動による樹脂粘度の変化と、それに伴う押出ムラを防げます。
PIDチューニングは、温度が安定しない問題を解決してくれる重要な設定です。ヒーターの運転を最適化することで、設定温度を正確に維持できるようになります。やり方は簡単で、ターミナルから数行のコマンドを打つだけ!詳しくは別記事で解説していますので、ぜひチェックしてみてください。
フィラメント径をノギスで測定し、スライサーで補正
フィラメント径が1.75mm±0.05mmなどと大きくばらついている場合、ノギスで測定した実測値をスライサーソフトに入力して押出量を補正しましょう。
- フィラメントの異なる箇所を3〜5カ所測定
- 平均値をスライサーに入力
- ロールごとに測定するのがベスト
面倒に感じるかもしれませんが、一度測定すれば同じロールを使っている間は設定を変える必要がないので、やっておいて損はありません!
スライサー設定対策
ソフトウェア設定で解決できる部分もあります。特にレイヤー高さの設定は、Zバンディング対策の要です!
レイヤー高さをリードスクリューのピッチと整数比に合わせる
これは「スライサー設定」でできる最も重要な対策です。あなたのプリンターのリードスクリュー(例:TR8×8で1回転8mm移動)を確認し、レイヤー高さをその移動量を割り切れる値に設定します。
例えば、1回転で8mm移動するリードスクリューの場合、レイヤー高さを以下のように設定すると効果的です。
- 0.1mm(80レイヤーで1回転)
- 0.2mm(40レイヤーで1回転)
- 0.4mm(20レイヤーで1回転)
このように設定すると、モーターがスムーズに動作しやすく、周期的なズレが解消されやすくなります。逆に0.15mmや0.3mmなどは避けた方が無難です。
Z-hopを必要最小限に
Z-hopが原因でZバンディングが生じている場合は、この機能をオフにするか、必要な高さ(例:0.1mm)まで下げてみましょう。
私の場合、Z-hopを0.3mmから0.1mmに減らしただけで、かなり改善しました。
完全にオフにしてしまうと、ノズルが造形物に引っかかるリスクがあるので、最小限の高さに留めるのがコツです。
実践例:改善前後の変化
実際にZバンディング対策を行ったプリンターのBefore/Afterは、感動ものです!写真で見るとその差は一目瞭然。
| 調整前(Before) | 調整後(After) |
| 層ごとに横線がくっきりと出ており、照明を当てると全体が光を不規則に反射し、波打っているように見えます。 | 表面がまるで射出成形のように均一で滑らかになり、レイヤー境界の段差がほとんど目立たなくなります。 |
| 特に円筒形などのカーブした部分に、定期的な縞模様が顕著に出ています。 | 光沢のあるフィラメントを使用しても、ムラなく均一に光を反射し、美しい仕上がりになります。 |
※Ender3 + Klipperの3Dプリンターで出力しました。
成功事例の鍵となったパーツ
私が実際に効果を実感したパーツはこちらです。
- TR8×8高精度リードスクリュー(そもそもの物理的な曲がりを排除)
- フローティング構造の導入(スクリューの揺れをZ軸全体に伝達するのを防止)
この2つの対策だけで、Zバンディングはほぼ完全に消えました!特にリードスクリューの交換は、効果が絶大なので最優先で試してほしいです。
まとめ:Zバンディングを防ぐ考え方
Zバンディングを根本から解決するための考え方は非常にシンプルです。それは、「Z軸をいかにブレさせずに真っ直ぐ、安定して動かすか」に尽きます。
一時的な設定変更でごまかすのではなく、原因のほとんどを占める「機械的精度」と「Z軸アライメント」に焦点を当てることこそが、解決への最短ルートです。
Z-Banding解消のための3大原則
- 「真っすぐ回す」: リードスクリューの曲がりを物理的に排除する。
- 「芯を合わせる」: モーター軸とスクリュー軸の芯を完璧に合わせ、偏心させない。
- 「上端を固定しない」: スクリューのわずかな揺れをZ軸全体に「横揺れ」として伝達しない。
この記事の手順を上から順に、一つずつ丁寧に試していけば、Zバンディングは改善します。
それでは、良い3Dプリンターライフを!