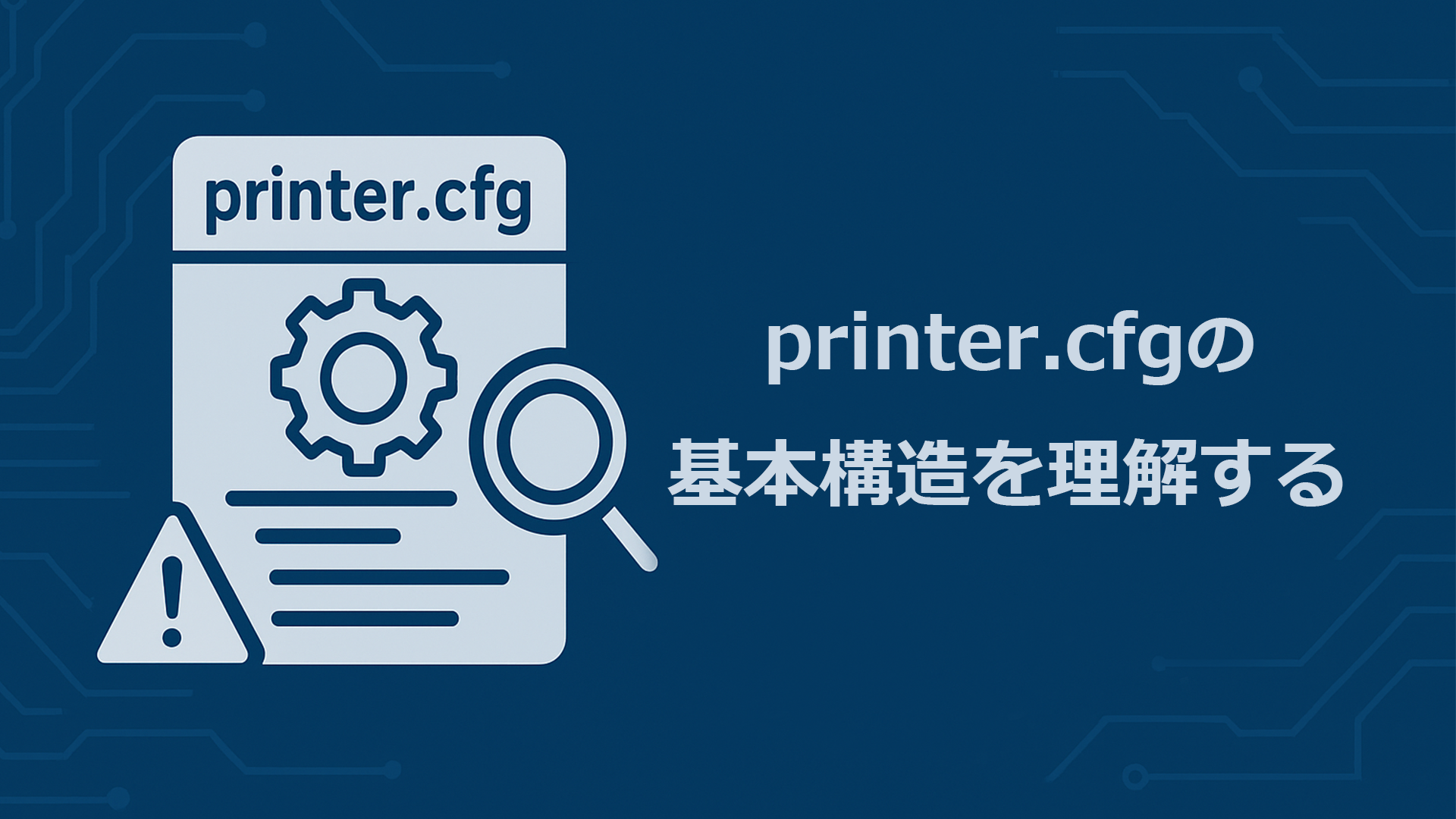「Klipperって最近よく聞くけど、結局なんなの?」 「Marlinと何が違うの?本当に導入する価値あるのかな?」
この記事は「Klipperって結局なに?」を最短距離で知りたい人向けです。深い設定や小難しいコマンドはひとまず置いて、私の経験から仕組みやメリット、注意点までをお届けします。
実際にEnder3にKlipperを入れて3ヶ月。良かったこと、正直ちょっと困ったことまで、包み隠さずお伝えしていきますね。
Klipperとは?まずは基本をおさらい
改めて説明すると、Klipper(クリッパー)は3Dプリンターを動かすためのファームウェアです。でも、今まで使っていたMarlinやRepetierとはちょっと違うんですよね。
一番の特徴は、頭脳を2つに分けていること。
Raspberry Piのようなホストコンピュータが難しい計算を担当して、プリンター本体のマイコン(MCU)はモーターやヒーターの制御に集中する。この役割分担が、Klipperの「速くてきれい」を支えています。
イメージしやすく例えると、料理長が「次はこう動いて、こう加速して」と事前に計画を立てて、シェフはそれを忠実に再現する。だから高速でも失敗しにくいんですね。
Klipperを支える3つの技術
Klipperが「ただのファームウェア」で終わらない理由は、最新技術をガンガン取り入れているから。特に覚えておきたいのがこの3つです。
- Input Shaping(共振補正)
- Pressure Advance(押し出し補正)
- マクロ機能
Input Shapingはプリンターの振動を予測して、表面の波打ちを抑える機能。「ゴースティング」と呼ばれる模様がほぼ消えるんです。
Pressure Advanceはフィラメントの押し出しの遅れを先読みして補正。角の「もっこり」や「ダレ」を防いでくれます。マクロ機能を使えば、印刷終了後に自動で電源オフ、フィラメント交換の自動化など、面倒な作業を自分好みに組めるのが便利。
これらの技術があるから、Marlinでは実現できなかった「速さと品質の両立」が可能になっています。
MarlinやRepetierとの大きな違いは、「どこで計算するか」です。Marlinは計算も制御もMCUで完結しますが、Klipperは計算をホストに任せることで、MCUは制御に専念できます。だから高速域でも形状が崩れにくいんです。
実際の導入プロセス:想像より簡単だった
さて、ここからが本題。私がEnder3にKlipperを導入した時の話です。
用意したもの
私が準備したのはこんな感じです。
- Ender3本体(もちろん)
- Raspberry Pi Zero 2W(ホスト用、約3,000円)
- FLY D5メインボード(32bit、約2,500円)
- TMC2209ドライバー(静音&高精度、4つで約2,000円)
- microSDカード(Raspberry Pi用、16GB以上)
- 安定した電源とUSBケーブル
他にもエクストルーダーや冷却ファンなど色々交換しましたが、Klipperの導入自体に必須なのは上記だけです。トータルで8,000円くらいの初期投資でした。
導入の流れ
手順は大きく分けて5ステップです。
- Raspberry PiにKlipperをインストール
- FLY D5ボードにKlipperファームを書き込み
- printer.cfgファイルを作成
- PIDチューニングとEステップ調整
- Input ShapingとPressure Advanceの設定
KIAUHというKlipper管理ツールを使えば、MainsailOSを簡単にインストールできて、Klipper + Mainsail(Web UI)の環境が一発で入ります。
ボードへのファーム書き込みも公式ドキュメントに従って進めるだけで、思ったより簡単でした。printer.cfgはプリンターの設定を書き込むテキストファイルで、サンプルをコピペして少しずつ調整していきます。
PIDチューニングとEステップで温度とフィラメントの押し出し量を最適化。
これが意外と大事です。最後に加速度センサーで振動を測定してInput ShapingとPressure Advanceを設定すると、ここで品質がガラッと変わります。
正直、「これ私にできるかな…」と不安でしたが、コミュニティの情報が充実しているし、つまずいてもすぐに解決策が見つかりました。
Ender3にKlipper + MainsailOSの導入方法をこちらで解説しています。ぜひご覧ください!
セットアップの手間が気になるなら、元からKlipperファームウェアが導入されている市販3Dプリンターがあります。Klipperがプリインストールされてるものが売られているくらいKlipperファームウェアは優秀なんです。
使い始めて1週間:こんなに楽だったのか…
導入して最初の1週間は、まさに感動の連続でした。
一番感じたのは、SDカードを抜き差しする必要がなくなったこと。スライサーで作ったG-codeファイルを、Wi-Fi経由でポンっと送るだけ。ブラウザからMainsailを開いて、「印刷開始」ボタンをクリック。
スマホからでも操作できるので、ソファーに座ったまま、ベッドに寝転んだまま、プリントを開始できます。これがこんなにストレスフリーだとは思いませんでした。
印刷速度も目に見えて上がりました。Marlinの時は、安定して印刷できる速度が40mm/s程度。それ以上速くすると、角が崩れたり表面がガタガタになったりしていました。
でもKlipperにしたら、100mm/s〜120mm/sでも余裕。Input Shapingのおかげで、高速域でも表面が滑らかなまま。最初は「本当かな?」と疑っていたんですが、実際にプリントしてみて納得。同じモデルが半分くらいの時間で完成するんです。
Mainsailの画面も思った以上に便利でした。温度グラフがリアルタイムで見られて、印刷の進捗が一目瞭然。カメラ映像でプリント状況を確認できるし、ファイル管理もドラッグ&ドロップ。
特に気に入ったのが、マクロボタン。ワンクリックで「ベッドレベリング」「ノズル交換用の加熱」「フィラメント交換」ができる。自分好みにカスタマイズできるのが楽しいです。
1ヶ月後:細かい調整で品質がさらに向上
使い始めて1ヶ月。この頃には、Klipperの設定にもだいぶ慣れてきました。
Input Shapingの威力を実感
加速度センサー(ADXL345)を取り付けて、Input Shapingのキャリブレーションをやってみました。
結果は…衝撃的。
今まで「仕方ないか」と諦めていた表面の波打ち模様(ゴースティング)が、ほぼ消えたんです。特に、文字やロゴが入った造形物の仕上がりが段違いに良くなりました。
設定自体は10分程度。printer.cfgに数行追加するだけ。この手軽さで、ここまで品質が上がるなんて…もっと早くやっておけば良かったです。
Pressure Advanceで角がシャープに
次に試したのが、Pressure Advance。
これは、フィラメントの押し出し量を先読みして調整する機能です。角を曲がる時、ノズルが減速するとフィラメントが余分に出てしまって「もっこり」するんですが、これを抑えてくれます。
最適値を見つけるのに少し試行錯誤しましたが、見つかった時の達成感はひとしお。角がビシッとシャープに決まって、「おぉ…!」と声が出ました。
マクロでの自動化も進みました。印刷終了後の処理(ノズルを退避→冷却→ファン停止→電源オフ)、フィラメント交換の手順、ベッドメッシュの自動取得など。特に印刷終了後の自動化は便利。深夜にプリントを開始しても、朝起きたらきれいに冷えて電源も切れている。消し忘れの心配がなくなりました。
3ヶ月後:もうMarlinには戻れない
そして現在。Klipperを導入して3ヶ月が経ちました。
数値で見る変化(ビフォーアフター)
具体的な数字で比較してみます。
| 項目 | Marlin | Klipper |
|---|---|---|
| 印刷速度 | 40mm/s | 120mm/s(2倍) |
| テストキューブの仕上がり | 角が少し丸い、表面に波模様 | 角がシャープ、表面滑らか |
| 失敗率 | 10回に1回くらい | 30回に1回程度 |
| SDカード抜き差し | 毎回 | ゼロ |
| 設定変更の手間 | コンパイル+書き込み(30分) | テキスト編集+再起動(1分) |
数字にすると、改めて「変わったなぁ」と実感します。
Marlinファームウェアを使っていたときは、印刷って少し面倒な「作業」でした。SDカードを持って行って、失敗しないかヒヤヒヤして、終わったら片付けて…。
でもKlipperにしてから、印刷が「楽しみ」に変わったんです。ソファーからスマホでポチッと開始して、気づいたら終わってる。この快適さを知ってしまうと、もう戻れません。
3ヶ月使ってみて、Klipperの本当の価値は「速度」や「品質」だけじゃないと気づきました。一番の魅力は、拡張性です。
マクロを自分好みに組んで、通知をDiscordやLINEに飛ばして、複数のプリンターを一元管理して…。やりたいことが、どんどん実現できる。「こうしたいな」と思ったことが、ちょっと調べればできてしまう。この自由度の高さが、Klipperを使い続ける理由になっています。
正直に語るデメリットと後悔した点
ここまで良いことばかり書いてきましたが、正直なところ、デメリットもあります。
初期費用がかかります。Raspberry PiとメインボードFLY D5で、合計8,000円くらい。決して安くはありません。ただ、私の場合はSDカードの抜き差しストレスと、印刷時間の短縮を考えると、十分元は取れたと思います。
月に10回印刷するなら、3ヶ月で90時間くらい時間短縮できた計算です。
最初の設定は少し難しいです。printer.cfgの編集や、PIDチューニング、Input Shapingのキャリブレーション…。正直、最初は「うっ…」となりました。特にプログラミングに慣れていない人は、ハードルを感じるかもしれません。
ただ、一度設定してしまえば、あとはほとんど触ることはありません。そして、コミュニティが充実しているので、分からないことはググればすぐ出てきます。ただし、ほとんど英語ですが、、、
電源の品質やUSBケーブルの相性で、通信エラーが起きることもあります。私も一度、安物のUSBケーブルを使っていて、印刷途中に止まってしまったことがありました。ケーブルを変えたら解決しましたが、こういう「見えにくいトラブル」があるのは事実ですね。
唯一後悔しているのは、「なんでもっと早く導入しなかったんだろう」ということ。少し設定を変えるだけでもコンパイルが必要だったのでその時間が、本当にもったいなかったです。
まとめ
Klipperを3ヶ月使ってみて、一番感じたのは「道具」から「相棒」に変わったこと。
ただプリントするだけじゃなくて、「こうしたらもっと良くなるかな」と試行錯誤する。その過程そのものが、楽しいんです。SDカードの抜き差しから解放されて、印刷は2倍速くなって、品質も上がって、運用も楽になった。この3ヶ月で、3Dプリンターとの付き合い方が根本から変わりました。
こんな人におすすめ
実際に使ってみて、こんな人にKlipperはピッタリだと感じました。
- SDカードの抜き差しにウンザリしている人
- 印刷速度を上げたい、でも品質は落としたくない人
- 自動化や効率化が好きな人
- 「もうちょっと何とかならないかな」と感じている人
SDカードの抜き差しから解放されるだけでも導入する価値があります。私の一番の動機でした。Klipperなら速度と品質の両立ができて、実際に2倍速でも品質が向上しました。
マクロで自分好みの環境を作れるので、カスタマイズの自由度が高いです。「もうちょっと何とかならないかな」と感じているなら、Klipperは「何とかなる」選択肢です。
こんな人は慎重に
一方で、こんな人は無理に導入する必要はないかもしれません。
- 今のMarlinで十分満足している人
- 初期設定に時間をかけたくない人
- とにかく安定性重視の人
満足しているなら、そのままでOKです。最初の壁は確実にありますが、越えた先の快適さは格別。Marlinの方が安心と感じる人もいますが、Klipperも十分安定しています。
「Klipperとは何か?」と聞かれたら、私はこう答えます。
「3Dプリンターとの付き合い方を、根本から変えてくれるファームウェア」
もし今、Marlinを使っていて「もうちょっと何とかならないかな」と感じているなら、一度Klipperを試してみてください。初期設定のハードルはありますが、それを越えた先には、今までとは違う3Dプリント生活が待っています。
きっと、戻れなくなりますよ。それでは、良い3Dプリンターライフを!